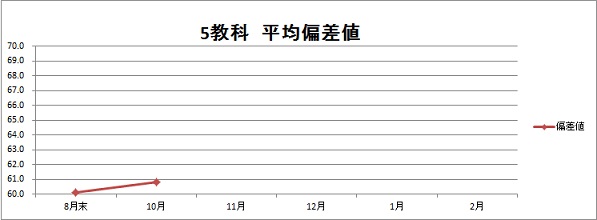数学については、勉強法等、書くことは色々あるが・・・
いつも通り、数学も「基本が大切だ!」ということを。
数学の成績がいい生徒の特徴と言われたら、
「間違えちゃいけない基本問題で間違えないこと」と答える。
超難関高校に受かる生徒が、 教科書レベルの問題を解けないことは絶対ない。
難関理系大学を目指していて、 センター試験の問題が解けないなんてあり得ない。
だから、数学の点数を上げようと思ったら、
まずは、基本的な問題を完璧に解けるようにすること。
これが最優先。
私も、関東圏内の有名私立の難問を授業でやったり、受験数学のテクニックに走りたい気持ちにかられることもある。
しかし、その前に…やるべきことが !!
数学は積み重ねの教科。
基盤がしっかりしていないとと、 どんなにテクニックを学んでも砂上の楼閣にしかなりませぬ。
※以下、私の数学勉強経験談。
大学受験時、
①数学の教科書を本質的に理解するようにしたこと(←最も難しい)
②「一対一の対応」という問題集を繰り返し解いたこと
この2つによって、飛躍的に数学の点数が上がった。
東大、京大実戦模試でも8割近くとれるようになっていた。
(そのせいで、理学部数学科なんてところに入ってしまったが…)
逆に、学校で配る、チャート式問題集や教科書併用問題集は量が多すぎて、身にならなかった。(茨城県内の、大学進学を目指す高校では、チャート式と教科書併用問題集の2冊を配付している。気合入りすぎて、消化不良では?どれだけの生徒がこなせているのか、甚だ疑問)
また、「新数学演習」という日本一番難しい問題集も解いたが、結局時間の無駄だったように思う。
今でも、ときどき大学入試問題を解いている。
東大でさえも近年、易化していて基本的な内容しか出ていない。
情報があふれ、特別な勉強が必要!と思ってしまうが、
まずは、教科書レベル。
それが出来ないと、話は先に進みませぬ。