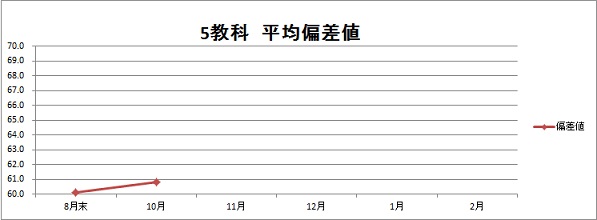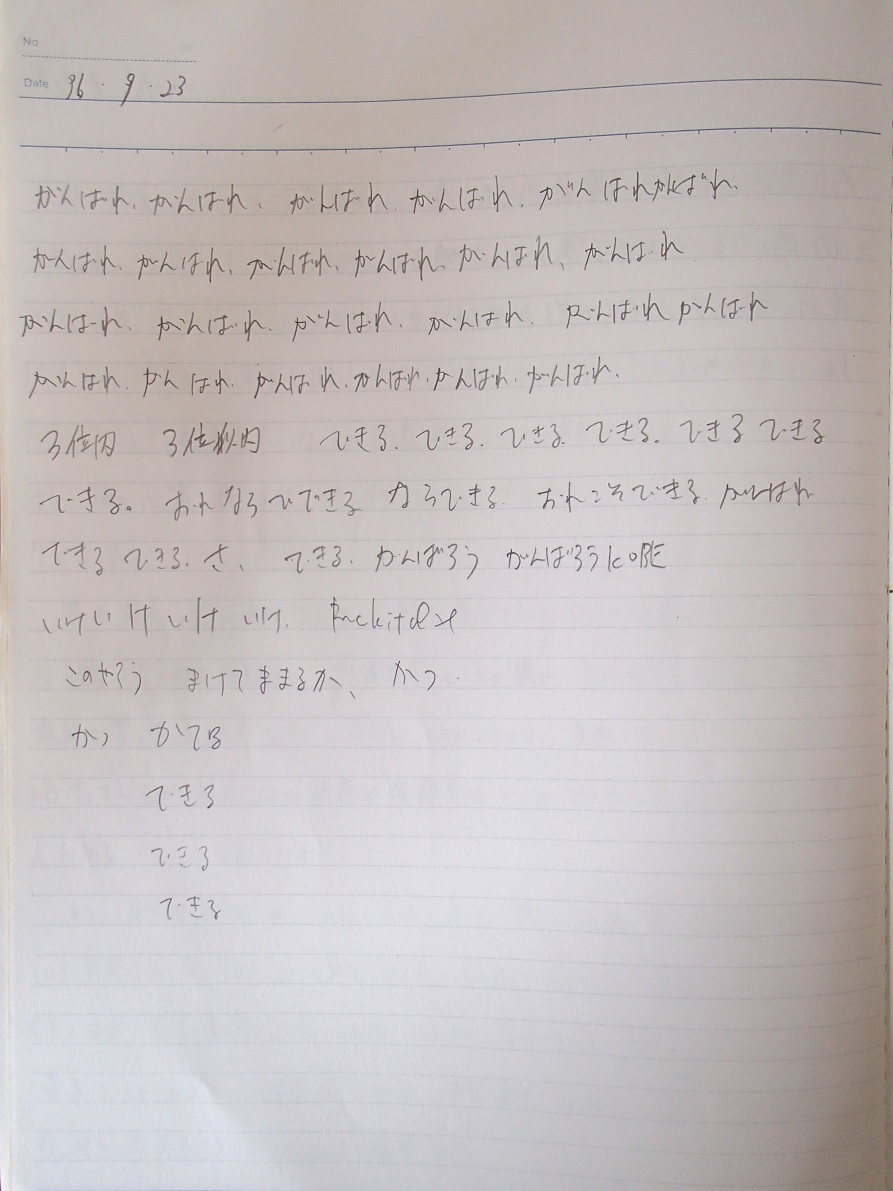今年も、恒例の平均偏差値を。
夏期後の8月末と10月のデータ。
人の出入りがあると信憑性がなくなってしまうので、これから受験を供に戦うメンバー、全員分をそのまま平均したもの。
現在の平均偏差値は、60ぐらい。
縦軸は強気に、なんと70まで取ってしまった・・・。
このデータを公表するのは、かなり勇気がいる。
というのは、いろんな塾の教室でこの平均偏差値を計算すると、
横ばいがほとんど。
上がっているように見える塾も、実は上がった人が目立っているだけだったりする。
そもそも、偏差値は相対評価なので、上がる塾もあれば下がる塾もある。
これは、頑張るしかない!!